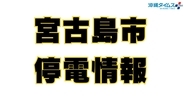中でも、済州所属のペク・ドンギュ選手が浦和所属の阿部勇樹選手に肘鉄をいれたことで物議を醸した。幸いにもこの乱闘でけが人は出なかった。だがけが人が出た場合、責任の所在はどうなるだろう。反スポーツ行為として、まれに発生してしまう「乱闘」は、法的側面ではどのような解釈になるのかを、アディーレ法律事務所の時光祥大弁護士に問い合わせた。

――スポーツにおける乱闘は、刑事罰に処されるのでしょうか。また法に抵触する際は、刑法のどの部分に触れるかについてお聞かせください。
「スポーツ内で起こったことでも刑法の適用がありますので、刑事罰の対象となります。ただ、警察や検察は悪質なものでなければ『団体の自治』を尊重して、逮捕や起訴するのはまれでしょう。
乱闘では相手を殴ったり、突き飛ばしたり、さらにはけがをさせたりする場合もあると思います。相手を殴る、突き飛ばすと、暴行罪(刑法208条)。けがをさせたら傷害罪(204条)になります。一方的に暴力を振るわれている状況で、自分やチームメートを助けるために殴り返した場合は、正当防衛(36条1項)や過剰防衛(2項)になる可能性もあります。
サッカーは提訴禁止?サッカー協会の規則は有効か
サッカーにおいて、競技中のけがによる法廷闘争は日本サッカー協会が禁止している。だが乱闘とは異なる事例であるものの、今年の5月にサッカーをプレー中に負傷により、裁判に発展した事例があると朝日新聞が報道した。
東京都社会人リーグでプレーする男性がボールを蹴ろうとした際、相手選手の足がすねに接触して骨折。2015年10月、相手選手に損害賠償を求め提訴した。2016年12月には、故意とは認められないものの、「走り込んで来た勢いを維持しながら、(相手選手は)ひざの辺りの高さまで足の裏を突き出しており、何らかの傷害を負わせることは予見できた」として、東京地裁は相手側に損害賠償を命じる判決を下した。
上述した規則から鑑みるに、日本サッカー協会は提訴を禁止しているため、提訴した場合は提訴した側に何らかのペナルティが課す可能性がある。しかし、理不尽な反スポーツ行為によって負傷した場合は法廷闘争が発生することも十分ありえるだろう。この提訴禁止は法的拘束力が有るのかについて時光弁護士に尋ねた。
――日本サッカー協会は「ピッチ上における紛争行為」について、提訴禁止を規定しています。この提訴禁止は法的拘束力があるのでしょうか。
「国民には、憲法上裁判を受ける権利(憲法32条)が保障されています。
では、規約で提訴を禁止することはできるのでしょうか。たしかに規約は加盟者全員に対するものであり、個別に提訴禁止の合意をしたわけではないので、無効のようにも思えます。ただその団体に加盟をしたということは、その団体の規約にすべて同意する前提で加盟をしたと判断されます。
この規定自体は選手が裁判をおそれることなく、思い切ったプレーをできるように設けられたもので、サッカーの発展のためには大切なものだと思います」
――ボクシングなどの格闘技では、リング禍(競技中若しくは競技終了後に競技が原因した死亡事後) が起きるケースもあります。そういった格闘技は試合前にリング禍が発生した際は、自己責任とする誓約書にサインする場合があります。そういった誓約書を書かなければ、他競技でのけがや事故は自己責任にならないのでしょうか。
「誓約書を書いていなくても、試合中に発生した偶然のけがは自己責任(暗黙の合意)だと考えられます。
このようにプレーによる負傷を提訴することは可能だが、実際に裁判を起こすことは難しいとの見解だった。しかしスポーツ内で刑法の適用事例はあるため、乱闘などの反スポーツ行為は刑罰に処される可能性があることも判明した。一般的に競技を運営する協会や連盟は高い自治能力を有するため、協会がピッチ上での闘争を回避するよう務めなければならない。ACLで起きてしまった乱闘が二度と発生しないよう、アジアサッカー連盟や日本サッカー協会の尽力に期待したい。
(高橋アオ)
取材協力
・弁護士法人 アディーレ法律事務所 時光祥大弁護士















![医療機器販売の(株)ホクシンメディカル[兵庫]が再度の資金ショート](http://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexnews%252Ffeed%252FTsr%252Fa8%252FTsr_1198527%252FTsr_1198527_1.jpg,zoom=184x184,quality=100,type=jpg)