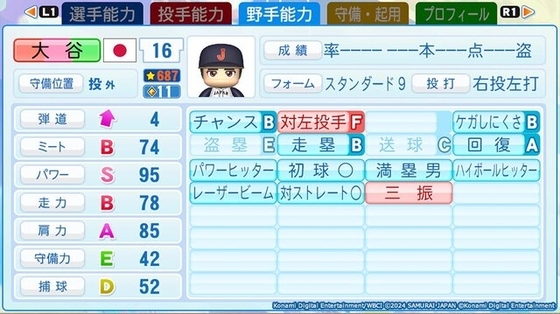実は、村岡花子の訳した『赤毛のアン』には、大きな謎がある。
第37章、最後からひとつ前の章。
マシュウが心臓発作で死んでしまう。
その晩、残されたマリラはアンに、いかに自分がアンを愛しているかを語る。
このシーンを、村岡花子は訳していないのだ。
村岡花子訳『赤毛のアン』では、こうなっている。
“その声を聞きつけたマリラが部屋にはいってきた。
二日たってから、マシュウ・クスバートは彼が耕した畑やたいせつに育てた果樹園を通って運ばれていった。”
(赤毛のアン』村岡花子訳・新潮文庫・昭和六十一年四月三十日七十四刷P376)
この部分、原文ではこうである。
Marilla heard her and crept in to comfort her.
"There?there?don't cry so, dearie. It can't bring him back. It?it?isn't right to cry so. I knew that today, but I couldn't help it then. He'd always been such a good, kind brother to me?but God knows best."
"Oh, just let me cry, Marilla," sobbed Anne. "The tears don't hurt me like that ache did. Stay here for a little while with me and keep your arm round me?so. I couldn't have Diana stay, she's good and kind and sweet?but it's not her sorrow?she's outside of it and she couldn't come close enough to my heart to help me. It's our sorrow?yours and mine. Oh, Marilla, what will we do without him?"
"We've got each other, Anne. I don't know what I'd do if you weren't here?if you'd never come. Oh, Anne, I know I've been kind of strict and harsh with you maybe?but you mustn't think I didn't love you as well as Matthew did, for all that. I want to tell you now when I can. It's never been easy for me to say things out of my heart, but at times like this it's easier. I love you as dear as if you were my own flesh and blood and you've been my joy and comfort ever since you came to Green Gables."
Two days afterwards they carried Matthew Cuthbert over his homestead threshold and away from the fields he had tilled and the orchards he had loved and the trees he had planted;
(ANNE OF GREEN GABLES)
高畑勲監督のアニメ『赤毛のアン』は、ほぼ原作に忠実である(神山妙子訳『赤毛のアン』を底本にしている)。このシーンの高畑版マリラはこう語っている。
「ふたりで力をあわせていくことだよ、アン。
村岡花子訳は、このマリラの言葉も、アンのセリフも削って、“二人はともに泣き、心から語りあい、慰めあった。”という一文ですませているのだ。
クライマックスといってもいい重要なシーンである。
アニメ版だと、観ている者も一番泣いてしまうシーンである。
そこをすっとばしてしまったのは、なぜなんだろう?
『東大の教室で『赤毛のアン』を読む』(山本史郎・東京大学出版会)は、『ホビット』『赤毛のアン』『ジェイン・エア』などを取り上げ、「人物造形」「視点」「プロット」といったポイントで「読み」を深めていく講義録。
第4章で、この謎を解明しようと試みる。
“ーでも、先生! 村岡花子がなぜそうしたのか、ぼくには理解できるような気がします。西洋ではどうだか知りませんが、そんなことは言わないのが日本的美学なんじゃないですか? わざわざ口に出すなんて気恥ずかしい、そんなこと言わないでも分かれよ、って感じで……”
という学生の意見を、山本史郎先生は、こう退ける。
“このような推測は、わたしには根拠が乏しいように感じられる。というのも、村岡が行っているのは「翻訳」であって、「翻案」ではないのだ。かりにモンゴメリーの話を日本の風土に移植して、別の物語を作ろうということなら、日本的な感情の動きへの配慮ということも考えることが可能だが、『赤毛のアン』はそのタイトルからして、日本とはまったく別の国で起きたこと、むしろ日本とは違うということを強調しているように思われるからである”。
そして、マリラの告白が削られたわけを以下のように解説する。
“マリラにあたえられている特徴は、児童文学であまりにおなじみの「こわいおばさん」という「フラット」な類型(タイプ)にぴったりとはまりすぎている”。
「フラット」というのは、フォスターが『小説の諸相』という本で解説している概念だ。
いわゆる「キャラが立ってる」というヤツだ(大雑把)。
キャラ立ちしているので、キャラが変化してはいけない。
もう一方が「ラウンド」。
多面性をもち、小説のなかで成長したり変化したりする人物だ。
“村岡は、主人公をきびしくしつけようと決意している気難しい田舎のおばあさんの口調として、そのような類型(タイプ)の人物に特徴的な口調こそがふさわしいと直感的に感じたのではなかろうか。”
で、村岡訳のマリラは、あのようなしゃべり方になり、「フラット」なキャラとなった。
マリラの告白シーンのセリフは、“「おっかないおばさん」という類型(タイプ)がしゃべる言葉にはそぐわない”ものになってしまう。だから、“第37章を、あのようなはしょった形にまとめあげたのではないだろうか”。
おもしろい仮説だ。
だが、それでも解けない謎がある。
実は、村岡訳が大胆に省略をきかせているのはマリラの告白シーンだけではない。
最後の章、第38章も、半分ぐらいはしょっているのだ。
たとえば、マリラの語るシーン。
“「何が希望なものか」マリラは苦々しく言った。「読書も裁縫も、目を使うことは一切できないなんて、いったい、何のために生きるんだい。いっそ見えなくなった方が、いや、死んだ方がましだよ。それに泣いてもいけないなんて。これから一人になったら、寂しいときには泣かずにはいられないよ。でも、今さら愚痴をこぼしても始まらないね。一杯お茶をいれてくれると、ありがたいよ。もうくたくただよ。このことは、当面、誰にも言うんじゃないよ。ちょっとでもだめだよ。いろんな人がやって来て、あれこれ聞かれたり、同情されたりして、説明するのは、まっぴらだからね」”(『赤毛のアン』松本侑子訳/集英社文庫)
こういった省略は他にもたくさんある。そうなってくると、フラットなキャラから逸脱するというだけでは説明できそうにない。
『快読『赤毛のアン』』(菱田信彦/彩流社)は、『赤毛のアン』を章ごとにとりあげ、作品の社会背景を紹介し、原文を検証しつつ、徹底解説した本だ。
ジェンダー観や階級意識がどのようにキャラクターに影響を与えているかについての考察も興味深い。
この本でも、この謎がとりあげられる。
“作品中でも最も重要なもののひとつといってもいいこの場面を、彼女はなぜ訳出しなかったのでしょうか。”
菱田信彦先生の意見は、『東大の教室で『赤毛のアン』を読む』の中で山本先生に退けられた学生の意見に近い(あの学生が菱田さんで、のちに教授になって本を書いたのではないかと、想像の翼が無駄にひろがる)。
さまざまな訳を比較したうえで、こう言うのだ。
“村岡はAnne of Green Gablesを「翻訳」してはいないということです。彼女は『赤毛のアン』という作品を「創作」しているのです。”
山本史郎先生とまっこうから対立である。
“彼女は自分がとらえたそのイメージが日本の読者にはっきりと伝わるようにと、そのことだけを念頭において訳文を作っています。そのため村岡は、英文を正確に訳すことにあまりこだわりません。ここを入れると自然な文章にならないと思うようなところは切り捨ててしまいます。結果として読者に伝わるものが大切なのであって、原文をどう訳すかは、極端にいえばどうでもいいのです。新しい時代の日本の若者のために良質な物語を求めていた村岡が、それにふさわしい作品を「創作」しようとしていたこと。それが彼女の「読み」がほかの誰とも異なる最大の理由ではないでしょうか。”
そして、想像にすぎないというエクスキューズのうえ、あの場面の省略について、著者はこう記す。
“日本人は、概して、親族を失った時でさえ、その悲しみを表に出さないことを美徳とするところがあります。とくに女性にそれを求める傾向があり、葬儀の際にとりみだしたり泣いたりしている女性に批判的な目を向けるメンタリティが存在するように思います。ましてや、村岡がこの作品を訳していたのは戦時中です。彼女の周囲には、戦火の中で親しい者を失いながら、その悲しみを抑えつけるしかなかった女性が何人もいたはずです。
村岡は、マシュウを失ったマリラとアンが激しく嘆き悲しんだり、余人がいないとはいえ思いを口に出して伝えあったりするさまを、「はしたない」、あるいは日本の読者に読ませるのに「ふさわしくない」と感じたのではないでしょうか”。
『花子とアン』はドラマなので、それをベースに想像の翼をひろげすぎるのもナンだが、ぼくはこう思う。
ドラマの中の花子なら、愛する者の死を嘆くシーンをこどもに読ませたくなかったのではないか。
"曲り角をまがったさきになにがあるのかは、わからないの。でも、きっといちばんよいものにちがいないと思うの。"(『赤毛のアン』村岡花子訳/新潮文庫)(米光一成)