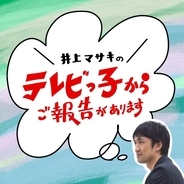脚本の橋田壽賀子は今年91歳、橋田とは半世紀以上のつきあいとなるプロデューサーの石井ふく子も今月1日で90歳を迎えた。テレビドラマの分野ではこれ以前にも、2013年にテレビ朝日で放送された時代劇「上意討ち 拝領妻始末」で、当時94歳の橋本忍が自作の脚本をリメイクした例はあるものの、まったくの新作、それも脚本家もプロデューサーも90代というケースとなると、おそらく世界的にも珍しいはずだ。
じつは「渡鬼」は、もともと橋田が“借金のカタ”として書き始めたものだという。先ごろ朝日新書より刊行された橋田の著書『渡る老後に鬼はなし スッキリ旅立つ10の心得』によれば、それは1989年、4歳下の夫が亡くなったときにさかのぼる。
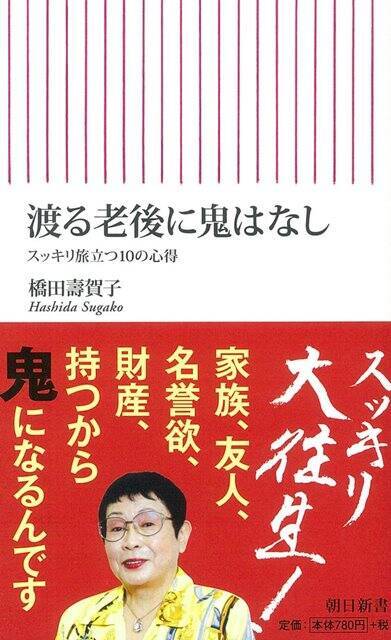
TBSの元社員で、定年退職後は橋田の仕事をマネジメントする事務所を立ち上げた夫は生前、彼女によく「おまえが死んだら『橋田賞』をつくる」と言っていたという。橋田は半ば冗談として聞き流していたものの、没後、夫が彼女の原稿料を株に代えて投資していたことがわかり、どうやら本気だったらしいとわかった。
ところが、財団の発足には思いのほか資金を要し、夫の遺産を注ぎこんでもまだ足りない。このとき不足分をTBSが貸すと申し出てくれ、橋田はその担保として1年にわたる連続ドラマの脚本を書くことになった。こうして生まれたのが「渡鬼」というわけだ。
主人公を大家族にしたのは、1年も続くドラマだけに、ネタが切れないようにするためだった。それも女であれば、嫁ぎ先で巻き起こるさまざまな家庭の問題を実家に持ちこむだろうとの目算で、岡倉家の5人姉妹が誕生したのだという。
一人で食事するほうが楽しいし、何より気楽
今回のスペシャルでは、5人姉妹のひとり小島五月(泉ピン子)が夫の勇(角野卓造)とともに切り盛りしてきたラーメン屋「幸楽」を、三代目として引き継いだ長女の愛(吉村涼)が両親に相談もなしに改装しようとしたことから騒動となる。それまで長らく働きずくめでやって来たのに、これをきっかけにやることがなくなってしまった五月。勇が仲間たちとおやじバンドの活動にのめりこむのとは対照的に、彼女には気軽に話のできる友達もいなければ、ひとりで旅行に出かける気も起きない。子供が完全に手を離れた母親が、その孤独と失望にどう立ち向かうかが本作の主なテーマとなるようだ。
橋田にもまた五月と同じく、長電話をしたり、しょっちゅう一緒に食事したりするような友達はいない。それでも、子供のときから友達づきあいが面倒くさかった自分には、むしろ一人でご飯を食べるほうが楽しいし、何より気楽だという。
だが、橋田に友達がいないわけではない。昔から旅行が好きな彼女には、旅先で出会った友達との距離感が最適という。脚本家として駆け出しの時代には、貧しいなか各地のユースホステルに泊まっては、そこで会った若い人の面倒を見たり、人生相談に乗ってあげたりしたという。そのころ知り合ったなかには、いまだに旅行についてきてくれる大事な友人もいる。日常的につきあいはないとはいえ、いざというときにつきあってくれる友達に恵まれているから、自分は寂しくないのかもしれないと、橋田は書く。今回の「渡鬼」で五月が孤独になるという設定には、そんな作者自身の他人とのつきあい方も反映されているのだろう。
結婚したら脚本家をやめて専業主婦になるつもりだった
橋田にいないのは、日常的につきあいのある友達だけではない。両親とも若いころに亡くしており、41歳で結婚したとはいえ、子供は結局できず、夫が死んでからは親戚づきあいもなくなったという。そもそも少女時代から父親と離れて暮らしていた時期が長く、家族団欒はほとんどなかった。しかし家族らしい家族を知らなかったから、自分はホームドラマが書けたのだと橋田はいう。
《むしろ家族がいたら、そうそうホームドラマなんて書けません。いないからこそ想像が膨らむというもの。
橋田は、脚本家として独り立ちし始めたころから「殺人」と「不倫」は書かないと心に決めた。また、視聴者として想定していたのは常に30歳以上の主婦層であり、だから、ホームドラマを書き続けてきた。
『渡る老後に鬼はなし』には橋田の半生についてもくわしく書かれている。それによれば、彼女は母親の束縛にたまりかねて猛勉強して、当時住んでいた大阪から東京の大学に進み、さらには映画会社の松竹に入って脚本家をめざした。そんな橋田の選択は、良妻賢母こそ女性の理想像とする当時の日本社会の常識とは相いれないものであったに違いない。
しかし一方で橋田は、結婚したら仕事をすっぱりやめ、子育てする“普通の奥さん”になろうと思っていたという。残念ながら夫とのあいだに子供はできなかったが、それでも常に夫を立ててきた。夫は飲んで帰ってくることもしょっちゅうだったが、夕食は食べる食べないにかかわらずつくっておかないと怒られるので、毎日用意していたという。そこには月給をいただいておきながら、何もしないのでは申し訳ないとの思いがあった。もっとも、原稿料の収入はある時期から夫の稼ぎを逆転するようになっていたのだが。
経済的に自立しながらも、自分のために稼いでくれる夫を常に立ててきた。橋田のなかではそんなふうに革新的なところと保守的なところが同居している。だからこそ彼女のドラマは幅広い層に支持されたともいえるのではないか。
橋田ドラマの特徴である長ゼリフも、家事などをしながらドラマを観ているであろう主婦たちのため、いったんテレビの前を離れてもストーリーが追えるようにする工夫だった。橋田はそんな自身を二流の脚本家と呼ぶ。同じ脚本家でも倉本聰や山田太一などは、セリフはそぎ落として磨いて、なるべくひとことで言わせようと考えているのだろうが、そうした能力は自分にはない。それゆえ橋田は、視聴者にわかってもらえることを優先して長いセリフを書き、あくまで「二流の道」を貫いたのである。
昨年、橋田はあるテレビ番組での発言が誇張され、ネットニュースで「引退宣言」と報じられてしまったことがあった。当人からすれば《「引退宣言」だなんて、私はそんなたいそうな身分ではありません。二〇一四年からパッタリ仕事の依頼が来なくなりましたから、むしろ“お払い箱”と言ったほうが近いのではないかしら》というのが正直なところらしい。それでもまた「渡る世間は鬼ばかり」の新作が放送される。おそらく橋田壽賀子は、今後も自分から引退はせず、依頼があるかぎり、作品を書き続けることだろう。
(近藤正高)