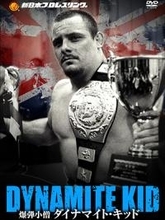文芸批評・時評集と言ってもいいこの本が、表題作としてなぜ役者さん(アイドル女優)を論じたものを選んだのかは、ここでは述べない。
中森さんは小説を書き、文化現象を分析し、アイドルと併走しつつアイドルを批評する。1980年代に〈おたく〉、90年代に〈チャイドル〉という語を作った。この本でも、いわゆる文学だけでなく、『あまちゃん』やAKB48といったサブカルチャーの話題を論じている。
この本を読むとわかること。まず中森さんは滅茶苦茶にものを知っていて、記憶力がいい。
中森さんの凄いところは、そのバラバラな情報どうしを、見立てによって結びつける運動神経なのだ。中森さんの文章に私が感じる魅力はこれだ。
〈菊池寛が秋元康なら、石原慎太郎は前田敦子か!?〉(「AKB48と文学」)
〈ジム・トンプスンは深沢七郎、色川武大と並ぶ“幻の中央公論新人賞作家”だ〉(「惑星トンプスン領からの伝令」)
〈「おたく」とは単にマンガやアニメの偏執狂的なファンの俗称ではない。個に自閉して、他者性を欠いた心性のありようの総体を言う(「おたく」の名付け親である私が言うのだから間違いない)。
子は父の背中を見て育つというけれど、本書所収の「東浩紀というキャラクター」で中森さんは、吉本隆明を批判した柄谷行人を批判した東浩紀を批判した宇野常寛、という例を出して、〈カリスマ批評家の文化継承〉は〈ホモソーシャルの愛憎劇〉でおこなわれる、と指摘している。
その吉本も花田清輝という先輩を批判したのは有名な話だし、花田は花田で読んでると小林秀雄という先輩を背後から撃っているようなところがある。
男の子のライフスタイル(思想)は、先行する男の子たちのライフスタイル(思想)への反撥として形成されるものだ。いわば「先輩を背後から撃つ」ことで世代交替が起こる。
さて、中森さんはこうやって見立て運動神経でどんどん言い切っていって、読者の世界を広くしてくれるけれど、博識で記憶力がよくて、そしてバラバラな情報どうしを結びつける書き手は、中森さん以前にもいた。
××(なんでもいい、たまたまそのとき話題にしているもの)の話をしていて、「とつぜん思い出したけど、××といえば…」と、その××から思い出したなにかの話題に逸れていって、その脇道に逸れていく「縁」のおもしろさで読者を楽しませる文章。
1960年代から70年代にかけてそういうのを書いて人気があった3人の先達が、すぐに思い浮かぶ。澁澤龍彦、寺山修司、植草甚一だ。『午前32時の能年玲奈』所収の文章のなかに、3人とも名前が出てくる。
澁澤・寺山・植草の文章がいくらリラックスしているように読めても、そのじつ、彼らの文章は昭和戦後──第3次教養主義ブームのまっただ中、およびその嵐が吹き止んでもまだ記憶が生々しい1970年代──に書かれたせいもあって、教養主義の暴風が吹きこんでこないように、窓につっかい棒をかっているような息苦しさがある。
澁澤・寺山・植草の文章は、だからリラックスしているときほど、人工的に閉じているので、逆の意味で読者を威圧している。
こんどは1980年代になって、その澁澤・寺山・植草的なものを、後続する「ニューアカデミズム」が背後から撃った。
中森さんは威圧しない。それは中森さんがだれも撃っていないからだ。
『午前32時の能年玲奈』所収の文章には、作家や批評家への愛ある罵倒がいくつも出てくるけれど、中森さんの文脈構成力のおかげで、〈ホモソーシャルの愛憎劇〉の舞台に乗らないようにできている(だからといって、中森さんが後輩によって背後から撃たれるのを避けることはできないけど)。
「東浩紀というキャラクター」のなかに、若手批評家の熱気の〈ピーク〉として、2008年の《早稲田文学》批評家10時間シンポジウムのことが、〈いや〜、あの頃は楽しかった。ただ、年長者の経験則として私は思ったものだ。
そのイヴェントに、批評家でもないくせに呼ばれた私は、会場では自分の程度にふさわしい拾い食い程度の発言をしただけだった。
私が中森さんに合ったのはこのときだけで、ものすごく覚えている。楽屋で中森さんに、連作短篇集『東京トンガリキッズ』(角川文庫)の1篇、永田ルリ子(おニャン子クラブ)ファンの少年が主人公の「たそがれにグッド・モーニング」が私に刺さってどうしても取れません、と告白したのだ。
私は、少年時代には三島由紀夫という人をただただ「人に認めてもらいたくて切腹までした、やり過ぎちゃった芸人」と決めつけていて、そんな人が書いたものを読むのはゴメンだと思って1字たりとも読まずにいたのだが(ジュネとかトゥルニエの戦争趣味なお耽美ド変態小説を愛読してたくせに『読まず嫌い。』過ぎる)、永田ルリ子さんが三島の文庫本を片っ端から読んでいるとTVでも紙媒体でもしつこく言うものだから自分もとうとう『豊饒の海』(新潮文庫)を読んでしまったという青春を持つ者である(その後三島の文庫解説を2冊書く機会に恵まれ、書いた。
シンポジウムの楽屋で中森さんは私に、終戦4日後にマレーシアで上官を射殺して自決した蓮田善明という批評家のことを教えてくれた。
その後新学社近代浪漫派文庫の『伊東静男 蓮田善明』で「有心(今ものがたり)」や「雲の意匠」を読んで驚き、なるほどあのとき中森さんが言っていたのはこれだったのか、と、ゆっくりと深ーい息を吐いたものだった。
そのときと同じ優しさと熱っぽさをもって中森さんは、『午前32時の能年玲奈』で『あまちゃん』やAKB48総選挙を論じている。読むとじっとしていられなくなる文章で。
直近のヒットコンテンツというものは、それに熱中した人にとっても、乗らずに傍目で騒ぎだけ聞こえてくる人にとっても、自分あるいは他人の熱気ばかり感じてしまって、うまく消化できていないものだ。
中森さんが論じ、こうやって編集されて本にまとめてくれたことによって、『あまちゃん』やAKB48総選挙といった国民的コンテンツが、他の文化現象と地続きのしかるべき位置を、私のなかで与えられたのだった。
「ここまでは俺がやったから、あとは自分で行動したら? 俺のいいぶんに文句があるなら、時間があったら聞くけどね」
この本を読んで、いわば中森さんにそう言ってもらったということだから、ちょっと行動してくるわ。
(千野帽子)