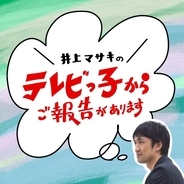同様の話は、昨年岩波新書から出た増井元『辞書の仕事』にも出てくる。そこでは、村上春樹の「無人島の辞書」と題するエッセイのほか、やはり「無人島に辞書を」派の代表格である井上ひさしが、持参するなら『広辞苑』と具体的に書名をあげていたことなどが紹介されている。もっとも井上は“自身があちこちに書きこみをした『広辞苑』”と断っており、それがいかにも日本語に終生こだわり続けた彼らしい。
無人島に辞書を持参したいという人は、古今東西を問わないようだ。現在はスペインの自治州であるカタルーニャのアウグスティ・カルベットという作家は、自分がもしロビンソン・クルーソーのような目に遭ったのなら、無人島にはせめて2冊の本を持っていきたいと、そのうち1つにプンペウ・ファブラの辞書をあげている。プンペウ・ファブラとは、『カタルーニャ語辞典』(1932年出版)を編纂した人物である。
■無人島は「ムジントウ」ではなかった!?
さて、ここまで繰り返しあげた「無人島」という単語を、あなたはどう読むだろうか? おそらく、ほぼ全員が「ムジントウ」と読むことだろう。しかし明治時代には、「ムニントウ」と読まれることのほうが多かったという。
漢字には「漢音」「呉音」「唐音」と3種の読み方がある。それでいけば「無」の漢音は「ブ」で呉音は「ム」、「人」の漢音は「ジン」で呉音は「ニン」。ようするに「ムジン」とは呉音と漢音が入り混じった読み方ということになる。
松井は、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典』(略称『日国』)を、祖父・父の仕事を引き継ぐことで完成させた人物だ。この辞典の特徴のひとつに、言葉の用例を文学作品などからとりあげ、時代順に並べていることがあげられる。編纂作業も、古代から現代まで膨大な文献から用例を採集することから始めたという。そこから浮き彫りになったのは、言葉がその読みや表記だけでなく、使われ方まで含めて時代によっていかに変わるかという事実だ。
面白いのは、「本来の意味からすれば誤り」といわれるような言葉の使い方を文豪たちが案外していたりすることだ。たとえば、「耳ざわり」という言葉。これは本来は、耳にいやな感じがすることを意味し、「耳障り」と書く。しかし現在では「耳ざわりがいい・悪い」とも表現され、「耳触り」と書かれることもある。これに対しては批判も根強い。
だが、川端康成はすでに戦前に、小説『童謡』のなかで《彼女等がお互ひの名を呼び交わす声などは、特殊な耳ざはりだった》と、「耳障り」とは異なる意味合いでこの言葉を用いている。
今年初めに第7版が刊行された『三省堂国語辞典』(『三国』)では、「耳触り」のように間違った言葉とされる語についても積極的に項目を立てている。これについては、同辞典の編集委員・飯間浩明の著書『三省堂国語辞典のひみつ』(三省堂)の「第2章 誤りと決めつけてはいけない」にくわしい。たとえば「的を得る」「汚名挽回」、あるいは「全然面白い」など「全然」のあとを否定形で結ばない用法は、いずれも“誤用”とされる。だが飯間はそれらを一つひとつ、過去の用例や類似語などと照らし合わせながら、「間違いとはいいきれない」と結論づけてみせる。
■辞書界の重鎮2人はなぜ袂を分かったか
国語辞典づくりを描いた三浦しをんの小説『舟を編む』(2011年)と、それを原作とした同名映画(2013年)がヒットすると、現実に辞書をつくっている人たちにもにわかに注目が集まった。
余談ながら『三国』とは対照的に、新語の採録には慎重で保守的とされるのが岩波書店の『岩波国語辞典』や『広辞苑』だ。
さて、ワードハンティングという言葉の名づけ親は、『三国』の初代主幹を務めた見坊豪紀(けんぼうひでとし)である。見坊の名前は、その後継者である飯間の著書だけでなく、先述の増井元や松村栄一の本にも登場する。常日頃から、言葉の用例を探し続けることを欠かさず、生涯にじつに約145万枚もの用例カードをつくったといわれる見坊は、まさに辞書界の伝説的人物なのだ。
この見坊と、同じく三省堂の国語辞典『新明解国語辞典』(『新明解』)の初代主幹の山田忠雄の関係に迫ったのが、佐々木健一『辞書になった男 ケンボー先生と山田先生』(文藝春秋)である。ほぼたった一人で辞書を編んだ希有な存在である2人は、東大国文科の同窓生であり、戦中・戦後と長らく一緒に『明解国語辞典』という辞書を編纂していた。それが1970年代に袂を分かち、おのおの『新明解』と『三国』を手がけることになる。
いったい両者の別れの理由とは何だったのか? 佐々木は、それを解く大きな鍵として、山田が『新明解』4版の「時点」の項目に書いた、《一月九日の時点では、その事実は判明していなかった》との用例をあげている。この「一月九日」は何か特別な日付ではないかというのが、佐々木の推理だった。その展開はじつにスリリングで、ミステリー小説を読んでいるようだ。
■「一生ものの辞書」などありえない?
この記事でとりあげたうち、辞書編纂に携わる増井元、松村栄一、飯間浩明の著書では、「時代を追うごとに言葉が変わるのは当然」という考えが強調されている。
そういえば、「辞書を編む人たち」の番組の終わりには、脚本家・向田邦子の《こんなに安くて便利で、しかもおもしろい本はありません。/バーゲンのブラウス一着分のお値段で一生使えるのです。/辞書はいちばんお買い得な品だと思います》という言葉が引用されていた。しかし「一生使える辞書」というのはもはやありえないのかもしれない。『日本国語大辞典』の松井栄一もこんなふうに書いている。
《昔は「良い辞書は一生ものだ」などといわれたものですが、世の移り変わりのあまりに激しい現在では、そんな言い方は通用しません》(『日本人の知らない 日本一の国語辞典』)
世の激しい変化といえば、いまやネット上の辞書を利用している人も急速に増えつつある。そのなかにあって、紙の辞書の存在意義は残されているのだろうか。番組では、三省堂の『大辞林』の編集者たちがまさにこの問題にぶち当たる。そこで最終的に彼らの出した結論は、大胆な方針の転換であった(具体的にそれがどんなものだったかは、ぜひ番組を見てご確認ください)。
しかし形は変わっても、辞書をつくるのが人間であることに変わりはない。今回紹介した本を読んでいくと、つくり手によってこれほどまでに辞書の中身は変わるのかと驚かされる。読後、あらためて辞書を引くと、各項目がそれまでとは違ったものに見えてきそうだ。
※「ETV特集 辞書を編む人たち」は、NHKオンデマンドでも2014年5月11日まで配信中(購入期限は5月10日まで)。
(近藤正高)